| 発電機のしくみ |
| 膨大なエネルギーが使われる原子力発電 |
| 原子力発電の基本的な問題点 |
| 原子炉の型と問題点 |
| 教材にある「何重もの安全のしくみ」の問題点 |
| 参考資料 |
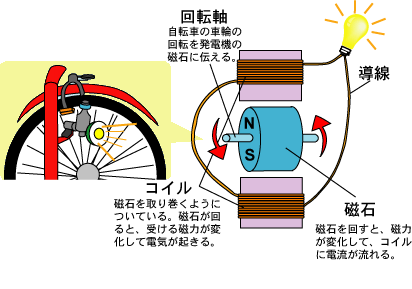 磁石の磁力線はNからSに向かっています。これを横切るようにコイルを動かすとコイルの導線に電気が流れます。この原理を利用して図1に示すようにコイルの内側に磁石をおき、それを回転させることによって電気をつくることが出来ます。自転車のダイナモから原子力発電まで、発電の基本原理は同じです。
磁石の磁力線はNからSに向かっています。これを横切るようにコイルを動かすとコイルの導線に電気が流れます。この原理を利用して図1に示すようにコイルの内側に磁石をおき、それを回転させることによって電気をつくることが出来ます。自転車のダイナモから原子力発電まで、発電の基本原理は同じです。
磁石を廻すための力としてなにを使うかにより発電方法が変わります。自転車の発電機には人力、水力発電にはダムなどにためた水力、風力発電では風力が使われます。また蒸気で回転させる方法もあります。蒸気を発生させるためのエネルギー源としては地熱を利用する地熱発電、石油、石炭、天然ガス等の化石燃料を使う火力発電、原子力を使う原子力発電等があります。
上に述べたように、蒸気の力で磁石を廻せば電気が出来ます。この蒸気を作るのに核分裂のエネルギーを使うのが原子力発電で、燃料として使われる物質はウラン235です。天然のウランの中には核分裂を起こさない(燃えない)ウラン238が99.3%と核分裂を起こす(燃える)ウラン235が0.7%含まれています。原子力発電には燃えるウラン 235の濃度を3%から5%まで濃くした(この過程を濃縮という)燃料が使われています(「少しの燃料で大きなパワーというけれど」を参照)。
ウラン235に中性子が一つ当たると図2に示すようにウランの原子核が二つにわれる核分裂が起こります。この分裂の時に中性子が2から3個飛び出し、同時に熱が発生します。核分裂の時にでてきた中性子の数をうまく調整していき次々にウラン235に当てると核分裂反応を定常的に起こさせることができます(これを臨界と言います)。その時に発生する膨大な熱でお湯を沸かし、蒸気を発生させ、タービンを廻し、発電します。
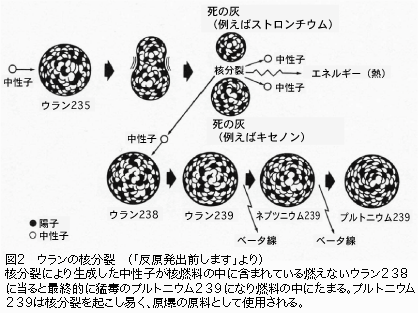
タービンを廻す蒸気は高温の方が効率がよく、火力発電では400度の蒸気が使われますが、原子力発電の場合は強い放射線によって機器が損傷されるため、2百数十度まで下げられます。核分裂反応によって発生する熱は2,400度(東京電力によると1700度)にもなるので2百数十度の蒸気を得るために、燃料棒の周囲をものすごい勢いで冷却水を流します。ダービンを廻した後の蒸気の熱は復水器で冷やされ温排水として捨てられます。原子力発電所が必ず海岸か大きな川、湖のそばにあるのは余分な熱を捨てるための冷却水がなければ発電が成り立たないためです。このように原子力発電はエネルギー転換効率が非常に悪い(約30%)発電方法ということになります。(火力発電の場合、コジェネレーションシステムを使うと80%以上の熱を利用出来ます。)すべての教材に原子力発電の長所として「二酸化炭素を出さない」から環境に優しいと書かれていますが、原子力発電所から出される温排水が河川、湖、海の水温を上げ、生態系や環境に悪影響を及ぼしていることは書かれていません。
原子炉の中に入れる燃料棒を図3に示します。ウラン燃料ペレットは直径約8ミリ高さ約1センチの円筒形をしています。これが長さ4メートル、厚さ1ミリ以下のジルコニウム合金の円筒形被覆管に数百個も詰められています。ウランは比重が大きく重いので、この針のような燃料棒は非常に注意して扱わないと自分の重さで壊れてしまう程のものです。
核分裂を起こさせるとこの燃料棒の中に放射性の核分裂成分(死の灰ともいわれる)が必然的にたまってきます。100万kW時の原子炉を1年間動かすと、一般人の摂取限度の2,500兆倍の放射性物質が炉心にたまります。その中にはプルトニウム239などのように長寿命(放射能の量が半分になる半減期が24,000年)の放射能も含まれています。これら毒性の強い放射性物質は生物の生活圏から完全に隔離しておかなければ危険なのですが、この技術はまだ確立されていません。
 核暴走の可能性 ー核反応の原理は原爆と同じー
核暴走の可能性 ー核反応の原理は原爆と同じー核分裂の連鎖反応を定常的に維持するため図3に示すように燃料棒の間に制御棒を入れ中性子の数を調整します。しかし、この連鎖反応を一定に保っておくのは非常に難しく、制御に失敗すると核暴走につながります。1986年4月に旧ソ連で起きたチェルノブイリ事故は制御に失敗して暴走にまでなった事故例です(詳しくはチェルノブイリ事故を参照)。事故の結果、原子炉周辺30kmは永久居住禁止区域となってしまいました。連鎖反応を一瞬にして起こさせるのが原爆で、原理的には原爆と原子力発電とは同じです。
死の灰から出される大きな崩壊熱は原子炉を止めても急には冷えません(図4)。高速で走っている車にブレーキをかけても急には止まらないのと似ています。制御棒を差し込んで反応を止めた後、発熱率が0.1%になるまでに約1ヶ月もかかります。これから分かるように、例え原子力発電を今日、直ちに止めたとしても、使用済燃料は10年以上にわたって冷却し続けなければならないのです。その間冷却に失敗すると燃料棒が溶けて放射性物質が環境中に放出され、大変な事故になる可能性があります。
一年間発電に使った燃料を10 年以上にわたって冷却し続けなければなりません。しかもそれが生物の生命にとって危険であり、何十、何百世代にもわたって消えないものであることはどの教材を見ても書いてありません。
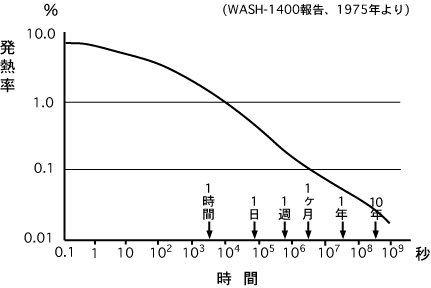
図4 核分裂生成物の崩壊による熱発生
日本で主に使われている原子炉には、加圧水型と沸騰水型があります。
 加圧水型原子炉の構造図を図5に示します。この型の原子炉はもともと原子力潜水艦に使っていた原子炉で、コンパクトに出来ているぶん損傷の進み方が激しいものです。冷却水は放射能を含む一次系と含まない二次系に分かれています。二次系の冷却水が蒸気発生器でものすごい勢いで蒸気になり、これが大きなタービンを廻し、発電機を廻し電気を作ります。それに伴う振動、熱的なひずみ等から蒸気発生器には非常な無理がかかっていて、損傷の進み方が激しく長い間にはぼろぼろになってしまいます。一次系では水の沸騰を抑えるために150から160気圧の圧力をかけています(150気圧というのは直径4メートルの原子炉容器の内面1平方メートル当たり1500トンもの力がかかることを意味します)。原子炉からの強い放射線にさらされている上に、高温、高圧であるため炉壁の脆化が起こり、崩壊するのではないかという心配があります。
加圧水型原子炉の構造図を図5に示します。この型の原子炉はもともと原子力潜水艦に使っていた原子炉で、コンパクトに出来ているぶん損傷の進み方が激しいものです。冷却水は放射能を含む一次系と含まない二次系に分かれています。二次系の冷却水が蒸気発生器でものすごい勢いで蒸気になり、これが大きなタービンを廻し、発電機を廻し電気を作ります。それに伴う振動、熱的なひずみ等から蒸気発生器には非常な無理がかかっていて、損傷の進み方が激しく長い間にはぼろぼろになってしまいます。一次系では水の沸騰を抑えるために150から160気圧の圧力をかけています(150気圧というのは直径4メートルの原子炉容器の内面1平方メートル当たり1500トンもの力がかかることを意味します)。原子炉からの強い放射線にさらされている上に、高温、高圧であるため炉壁の脆化が起こり、崩壊するのではないかという心配があります。
この形の原子炉で大きな事故を起こした代表的な例は、スリーマイル島(TMI)原子炉(TMI については原発事故参照)と、美浜原発2号炉等があげられます。
 沸騰水型(BWR)原子炉の概念図を図6 に示します。この型の原子炉は加圧水型と違い、一次冷却水、二次冷却水の区別はなく、原子炉の中で直接お湯を沸かし蒸気を作っています。この蒸気を気水分離器という装置を使って取り出してタービンを廻し発電します。その結果、沸騰水型原子炉ではタービンの外側まで色々な放射性物質で汚れます。そのため労働者被ばくが大きな問題となります。(原発で働く人々を参照)また、図からわかるように原子炉から出た蒸気は大きなパイプを通ってそのまま格納器の外に出ていますから、万一パイプに破断が起きると原子炉からの放射能が直接環境中に放出されることになります。
沸騰水型(BWR)原子炉の概念図を図6 に示します。この型の原子炉は加圧水型と違い、一次冷却水、二次冷却水の区別はなく、原子炉の中で直接お湯を沸かし蒸気を作っています。この蒸気を気水分離器という装置を使って取り出してタービンを廻し発電します。その結果、沸騰水型原子炉ではタービンの外側まで色々な放射性物質で汚れます。そのため労働者被ばくが大きな問題となります。(原発で働く人々を参照)また、図からわかるように原子炉から出た蒸気は大きなパイプを通ってそのまま格納器の外に出ていますから、万一パイプに破断が起きると原子炉からの放射能が直接環境中に放出されることになります。
大事故を起こした旧ソ連のチェルノブイリ原子炉は沸騰水型原子炉の亜型でした。
原子炉に危険性の高い放射性物質がたくさんたまるためと、核爆発の危険性を常に持つため、原子力発電の安全管理は幾重にもなされていなければならないことは誰が見ても明らかです。そのためにいわゆる「何重もの安全のしくみ」があるわけですが、そのしくみ自体に問題があったり、しくみがうまく働かなかったりしてこれまでに深刻な事故が起きてきました。これからも原子力発電を続けるかどうかの選択を迫られる生徒たちには考える基盤となる事実を教える必要があります。しかし、残念ながらそのような問題点はどの教材を見ても書かれていません。主な問題点を挙げてみます。
「原子炉を停止する必要がある場合には、制御棒を一度に入れて原子炉を自動的に止める装置が設置されている」と説明されています。しかし、原子炉の熱はすぐには下がらないことは、「炉心の大きな崩壊熱と冷却の必要性」を読んでいただければ分かります。その上チェルノブイリ事故のように制御棒自身の設計ミス もあります。原発は前もって実験出来ないような大がかりな施設であるために、実際に運転して事故が起きてみないとわからないことが多いのです。
「非常用炉心冷却装置(ECCS)がはたらいて大量の水で原子炉を水づけにして冷やす」と説明されていますが、これが計算通り働かずに事故になった例は書かれていません。
美浜原発2号炉の事故。これはPWR型の事故です。蒸気発生器細管という管が破裂してちぎれてしまった事故です。このときには肝心のECCSはうまく働きませんでした。
アメリカのスリーマイル島の事故の時は運転員が原子炉に本当は水を入れなければならないのに逆にECCSを絞り込んで水が入らないようにしてしまいました。そのため燃料棒が溶けてしまって、すんでの所でチャイナシンドローム(地球の裏側まで突き抜ける程の大きな事故のたとえ)というとても恐 ろしい事故になるところでした。
2002年には浜岡原発でECCSにつながる配管が水素爆発により破断しました。
・第1の壁:ペレット、「燃料のウランを固めたもの。」
平常に運転しているときでもクリプトンやキセノンなど揮発性の放射能は燃料棒からしみ出して被覆管との隙間に溜まっているので、これらの放射能に対しては壁とは言えません。
・第2の壁:燃料棒(被覆管)
「350個のペレットが特別丈夫な金属の管の中に入れられている。」
とありますが「特別に丈夫な金属」といわれているのはジルコニウムという金属です。これを使う理由は核分裂の時にでてくる中性子を吸収しにくいためです。 この被覆管の厚さは0.8〜0.9mm。ペレットの半径は約4mm、燃料棒の半径はやく6mm。ペレットの中心は2400度で、燃料棒の外側は280 度、6mm程度の間で約1700度近くの温度差があります。従って燃料棒を外からものすごい勢いで冷やしているわけです。もし冷却水が漏れて故障が起これ ば燃料棒はどんどん熱くなってしまいます。そして850度になるとジルコニウムは水と反応して燃え出して、放射能は外に漏れてきます。ジルコニウムが燃え ると水素が出来、水素爆発の危険がでてきます。スリーマイル原子力発電所事故では実際にこれが起きました。このようにジルコニウムを使うことは危険を伴いますが、他に適当な金属がないためにやむを得ず使っているのです。
「第3の壁、第4の壁、第5の壁があって万が一燃料棒を包んだ被覆管から放射性物質が漏れても放射能を閉じこめる」?
分かりやすいようにという親切な配慮からか、原子炉につながっているすべての配管を省略して原子炉を閉じこめた絵が描いてあります。もしこのように原子炉が閉じこめられていたら、燃料を入れたり出したり、原子炉からタービンを回す蒸気を取り出したり、制御棒をコントロールしたり、冷却水を送り込んだり出来るわけがありません。
実際にはこれらの目的のために何本もの太い管や細い管がこの壁を通っています。特に多いのは原子炉の下の部分で、ブレーキの役目をする制御棒の穴が100 個くらい、炉心の中性子をモニターするための穴が30個もあります。制御棒を入れるための管をハウジングといいます。浜岡原発の1号炉では、ハウジング と圧力容器との溶接部にひびが入っていてるものが多く、その一部から原子炉の水が漏れていました。もちろん水が漏れていれば放射能も漏れだします。
本当の意味で最後の砦になるのは格納容器だけですが、常に強い放射線と高熱にさらされており脆化が進みます。従ってこれがどんな爆発にも耐えられるという保証はありません。スリーマイル島原発事故の時、水素爆発に耐えられたのは、近くに飛行場があるため、飛行機の追突に耐えられるように世界一頑丈に作られていたためでした。
燃料集合体は炉心シュラウドというステンレス製の直径5.6メートル、高さが6.7メートルもある大きな筒にすっぽりと包み込まれています。定期検査で この炉心シュラウドにひびが入っているのが見つかりましたが、原子力保安院も東電も2年以上もずっとその事実を隠しておいたことが分かり、大きな問題にな りました。
さらに「原子炉を密閉するための部屋」であるはずの建家で気密性テストとを行いましたが、東電と日立製作所はそのデータをごまかしていました。
このように五重の壁といっても、一つ一つ検討すると、多くの問題をかかえていて、安全とはほど遠いことが分かります。このような問題点を隠して安全と教えて良いものでしょうか。
『原子力』図面集 日本原子力文化振興財団
『反原発出前します』反原発出前のお店・編 高木仁三郎・監修 七つ森書館 1993年
『海の声を聞く』市民論文「北海道泊原子力発電所における温排水による沿岸水温の上昇について」 斉藤武一著 七つ森書館 2003年
『原発事故 その時あなたは!』 瀬尾健著 風媒社 1996年
